誰でも家計簿は知っています。しかし今一度、簡単におさらいをしておきましょう。
そもそも家計簿は明治時代に日本初の女性ジャーナリストが考案したと言われています。
既に生まれてから100 年以上が経ちました。
時代とともに新しい家計簿が生まれました。今出ている家計簿の形態は様々です。
従来の手書きタイプの家計簿、パソコン用家計簿ソフト、自作のオリジナル家計簿があります。
一方、インターネットの急激な進歩によりオンライン家計簿が現れました。
その他にも細かく分類すると、まだまだあります。昔からある「袋わけ家計簿」も健在です。
一長一短ありで、どの家計簿がベストということはありません。
個人によって、家計簿をつける目的が違いますし、生活環境や嗜好も当然違ってきます。よって、最も自分にふさわしいものを選択することが重要です。
ある統計では、家計簿をつけている人とつけていない人では、年間30万円程出費の違いがあることが分かっています。この結果は、やはり家計簿はつけた方が良いことを物語っています。
そして、今のようなご時世ではなお更のことです。
◆目的
家計簿を始めるきっかけや目的は人によって違います。
集約すると主な目的は次のようになります。
 ・収支(収入/支出)の把握
・収支(収入/支出)の把握
・お金の管理
・無駄使い防止と節約
・予算を立てる
・将来の指針と目標
既に始められているあなたはどれに当てはまりますか?
家計簿を活用することで、収支が把握でき、お金の管理ができます。
何が無駄な出費であったか分かってきます。その反省から、節約の姿勢が生まれてきます。
記帳によって、今後の収支改善や予想が可能となるので予算が立てられます。
将来のライフプランや具体的な目標を設定できます。
◆形式
家計簿は家計の収支(収入と支出)を記録する帳簿のことを指します。
厳密な基準やルールがないので形式は様々です。
自分なりに家計の収支が分かれば良いのです。
記入項目としては、収支が発生した[日付]、[費目]、[収支金額]が基本です。
メモ欄として[備考]がついているものが一般的です。
更に、[費目]を細かく分類して、[内訳]、[品名]が追加されることがあります。
※帳簿は金銭や出品の出入りを記述した帳面のことです。
※費目は収入や支出を使い道によって分類した名目です。
家計簿記入の具体例です。
・[日付]:5 月10 日
・[費目]:食費、[品名]:肉、[内訳]:ひき肉
・[収支金額]:500 円
・[備考]:佐藤肉屋、安売り
各項目ごとに記入します。
| 日付 | 費目 | 内訳 | 品名 | 収支金額 | 備 考 |
| 5月10日 | 食費 | 肉 | ひき肉 | 500円 | 佐藤肉屋、安売り |
[収支金額]については、 [収入]と[支出]に分けると見やすくなります。
| 日付 | 費目 | 内訳 | 品名 | 収入金額 | 支出金額 | 備 考 |
| 5月10日 | 食費 | 肉 | ひき肉 | 500円 | 佐藤肉屋、安売り |
記入が何度も発生するので、表形式の様式になります。
| 日付 | 費目 | 内訳 | 品名 | 収入金額 | 支出金額 | 備 考 |
| 5月10日 | 食費 | 肉 | ひき肉 | 500円 | 佐藤肉屋、安売り | |
| 5月10日 | 食費 | 野菜 | 玉ねぎ | 350円 | 田中八百屋 | |
| 5月20日 | 光熱費 | ガス | 2,500円 | 4月分 | ||
| 5月23日 | 光熱費 | 電気 | 4,530円 | 4月分 | ||
| 5月25日 | 給料 | 75,000円 | 5月分パート代 | |||
| 5月31日 | 家賃 | 50,000円 | 6月分 |
上記の形式が家計簿の基本形式です。
更に項目を追加したり、減らしたりして、自分なりに使いやすいようにアレンジして使用します。
例えば、[初期予算]や[初期残高]を事前に設定することで、[残高]という項目を追加します。
| 日付 | 費目 | 内訳 | 品名 | 収入金額 | 支出金額 | 残高 | 備 考 |
| 5月10日 | 食費 | 肉 | ひき肉 | 500円 | 29,500円 | 佐藤肉屋、安売り | |
| 5月10日 | 食費 | 野菜 | 玉ねぎ | 350円 | 29,150円 | 田中八百屋 | |
| 5月20日 | 光熱費 | ガス | 2,500円 | 26,650円 | 4月分 | ||
| 5月23日 | 光熱費 | 電気 | 4,530円 | 22,120円 | 4月分 | ||
| 5月25日 | 給料 | 75,000円 | 97,120円 | 5月分パート代 | |||
| 5月31日 | 家賃 | 50,000円 | 47,120円 | 6月分 |
記帳データより、次のような集計値が期待できます。
・日/週/月/年単位の集計値
・費目/内訳/品名単位の集計値
・収入/支出金額の集計値
・残高、黒字/赤字判定
※集計値には、基本的な合計値の他、最大値、最小値、平均値などがあります。
◆記帳
家計簿は本来、お金が出入りした[日付]、[費目]、[金額]が記帳できれば済むはずです。
しかし、初心者が実際に記帳すると、困ってしまうケースが結構出てきます。
その代表的なものを挙げます。
・費目の選択
・金額の厳密性
・消費税の扱い
・収支の合計が合わない
・残高が合わない
始めた頃は、費目を何にするか迷います。
金額については1円単位で処理すること自体なかなか根気が要る作業です。
消費税を税込、税抜にするかで迷ってしまいます。そもそも消費税を記帳の対象にするかです。
一方、しばらく続けていると収支や残高が合わなくなってきます。
このような場合、どう対処するか個人差があって、これが正解というものがありません。
しかし、長年つけている方は自分なりに工夫してうまくやっています。
継続することで序々に自分なりの記帳スタイルが生まれてきます。
◆分析
手間と時間をかけて記帳した家計簿、しかし、これで終りではありません。
その貴重なデータをそのまま放っておくのは大変勿体無いことです。
データを基に分析という大事な仕事が残っています。
分析によって、無駄使いや節約の状況、そして、全体の収支状況が分かってきます。
節約するにはどうしたら良いか検討や判断することができます。
毎月の予算や年間の収支計画を立てることができます。
分析から反省と学習を重ねることで、無駄使いも減り、節約志向が自然と身につくでしょう。
お金の使い方がうまくなります。
今まではお金を使うたびに気が塞いでいたことでしょう。
しかし、「決して無駄使いはしていない」という自覚があると、お金を使うことも節約と同様に楽しくなります。
お金を使うのが楽しい、節約が楽しい、これこそまさに至福の喜びと言えるのではないでしょうか。
記帳を継続することでデータが蓄積されます。そのデータがあってはじめて分析が可能となります。
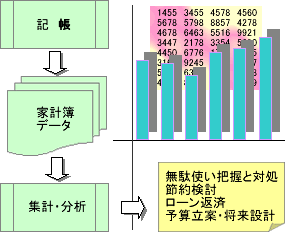
集計と分析によって、今後の見通しがはっきりしてくるので、予想や計画が立てやすくなります。
◆無駄使いと節約
家計簿をつけなくても家計をやりくりして生活している人はいます。
毎月の収支がほぼ決まっていれば、家計簿がなくても大雑把に把握できます。
「私の今月の給与はこれだから、家賃はこの金額で、食費にこの位、・・・、貯蓄にはこの位回して、
結局現金はこの位残るのかしら?」と、大体こんな感じでしょうか。
余裕のあるうちはこのような概算の目論見で結構でしょう。
しかし、昨今の時勢を考えて下さい。
不況、就職難、終身雇用問題、そして年金システム崩壊など、不確定材料が多過ぎます。将来にわたって今の状況が永続するという保障はありません。将来に備えることが賢明です。
やはり家計簿は必要となってきます。
記帳することで、現状の収支をしっかり把握できます。
家計データとして数値化してあるので、無駄使いや節約に対する確固とした判断が生まれてきます。
分析で予算や目標が立てられるので、将来の見通しがはっきりして、日常生活に活気が出てきます。
集計表やグラフ機能を備えた家計簿ソフトであれば、過去と現状の収支比較が一目で把握できて便利です。
家計簿を長期継続することで、お金の使い方は必ずうまくなります。
無駄な出費は控えるようになり、節約のコツが分かってきます。
「えっ〜、昔の私って、こんな無駄使いしてたんだ!」とはっきり自覚できるようになります。
無駄使いと節約は表裏一体です。節約とは無駄使いを失くすことです。
世の中には、節約やケチの達人と呼ばれる方がいらっしゃいます。「そこまでやるか」といったかなり極端な姿勢を見受けますが、見習うべきことは沢山あります。
節約は大事ですが、始めから達人のマネは無理、自分相応に分をわきまえることが肝心です。
◆継続
家計簿は誰かに言われて強制的に記帳している訳ではありません。止めるのも続けるのも自由です。
時間の制約もありません。自分の好きな時間にやれます。
しかし、どうしても継続できなくなるケースが出てきます。
一般に家計簿は全て記帳するという概念が定着しています。しかし、初心者にこの概念は禁物です。
家計簿を始めた頃はやる気満々なので几帳面に全て漏れなく記帳しようとします。
本来ならこれが理想ですが、最初からこのような姿勢では長く続かない可能性が高いといえます。
最初から完璧に記帳する必要はないのです。寧ろ、大雑把な方が長く続けることができるでしょう。
最初は完璧より大雑把な記帳と割り切りましょう。
慣れてきたら序々にステップアップしていけば良いでしょう。
各人の条件は違いますが、自分に合った記帳のルール化が必要となります。
幾つかルール化の例を示します。
 ・テスト期間を設ける(3 日、1 週間、1 ヶ月)
・テスト期間を設ける(3 日、1 週間、1 ヶ月)
・記帳インターバル(3 日、1 週間、10日)
・記帳対象(公共料金、食料、衣料)
・収支(収入だけ、支出だけ)
・金額制限(100円以下はつけない、1 万円以上はつけない)
・消費税(税込、税抜一括、つけない)
自分にふさわしいルールが決まったら、序々にステップアップしていけば良いのです。
始めから全てをしようとせず、序々に馴らしていきます。
家計簿で最も大事な点は継続です。目先のことにとらわれない事です。
ある段階まで継続できれば、もう家計簿なしの生活は考えられなくなります。
それを目標に頑張りましょう!
以上、家計簿について簡単なおさらいでした。
[スッキリかんたん家計簿]では、さらに詳しく家計簿の基本について説明しています。